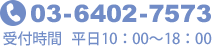近年、ハラスメント行為が問題となっており、企業でもルールを見直すケースが増えています。とくに、パワハラは「指導」と間違えやすいため、正しく理解することが重要です。 本記事では、パワハラと指導の違いとあわせて、パワハラになるパターンや正しい指導の方法について解説します。パワハラ防止を検討している方は、ぜひご一読ください。
パワハラと指導の違いとは?
「パワハラ」と「指導」は、一見似ているように思われますが、その目的や意図は大きく異なります。まずは、それぞれの概要を詳しく解説します。
パワハラは相手に苦痛を与える行為
パワハラは、パワーハラスメントの略称で、職場において優位な立場を利用して、相手に不必要な苦痛を与える行為を指します。業務上必要性のないことや、個人生活や人格を否定する言動などもパワハラのひとつです。 こうした行為は、職場の健全な環境を損ない、従業員の就業意欲やメンタルヘルスに悪影響を及ぼします。
指導は相手の成長を促す行為
指導とは、相手の能力やスキルを向上させるために行うアドバイスやサポートです。企業においては、上司が部下に対して業務の進め方や改善点を具体的に伝え、成長を促すことが指導の本質といえます。 たとえば、業務でミスがあった際に、ただ叱責するのではなく、どこに問題があったのかを説明し、解決策を提示する必要があります。適切な指導が行われれば、従業員は業務の理解を深め、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。 パワハラとは異なり、指導は職場の雰囲気を良好に保ちながら、従業員の成長を支える重要な役割を持つ行為です。
パワハラに当てはまるパターン
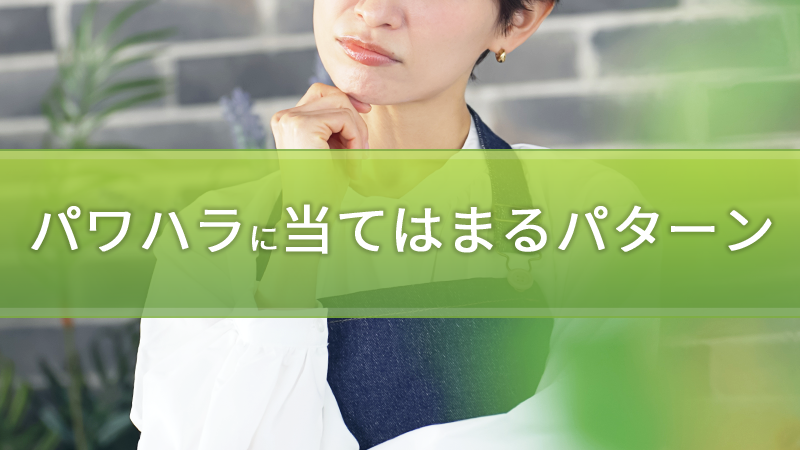
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」では、ハラスメントを6つの型に分類しています。気付かないうちにパワハラをしないために、どのような行為が該当するのかを知ることが大切です。ここでは、パワハラとみなされる行為を6つ解説します。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」
(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/)
相手の身体にダメージを与える
相手の身体を直接攻撃し、ダメージを与える行為は、パワハラとみなされます。たとえば、殴打したり蹴ったりといった暴行だけでなく、ものを投げつける行為などもパワハラのひとつです。 こうした直接的な暴力を伴う行為は、被害者に対して深刻な影響を与えるため、決して許されるものではありません。また、職場環境を悪化させる可能性があるほか、刑法上の暴行罪や傷害罪に該当する場合もあります。
言葉で精神的ダメージを与える
職場において、言葉で相手に精神的ダメージを与える行為は、パワハラの精神的な攻撃に該当します。具体的には、脅迫や侮辱、名誉毀損など、相手の人格や尊厳を傷つける言動が挙げられます。 たとえば、上司が部下に対して「お前は無能だ」などと繰り返し罵倒した場合は、パワハラとみなされるでしょう。こうした言葉による攻撃は、被害者の自尊心を著しく損ない、うつ病や不安障害などの精神的な問題を引き起こす可能性があります。
個人の性格を否定する
相手の人格や性格を否定して、精神的な苦痛を与える行為もパワハラのひとつです。たとえば、部下に対して「暗い性格だから仕事ができない」といった発言をした場合はパワハラに該当します。 また、性的志向や性自認などLGBTQに関連する言動、学歴や国籍などによる差別についても同様です。こうした言動は、被害者の自尊心を傷つける行為であり、メンタル面の不調につながる可能性も否めません。
集団から孤立させる
特定の従業員を集団から孤立させる行為は、人間関係からの切り離しに該当します。具体的には、上司や同僚による無視や仲間はずれ、業務からの排除などが挙げられます。 たとえば、挨拶をしても返事をしない、必要な情報を共有しないといった行為はパワハラであり避けるべきです。場合によっては、被害者に対して仲間外れをしたくないと思う従業員も、上司の命令に逆らえず状況が悪化するケースも少なくありません。 こうしたパワハラが横行すると、被害者の精神的な健康を害するほか、職場全体の信頼関係も崩壊します。
過小な要求を出す
過小な要求とは、業務や組織の運営上、客観的に見て妥当であると判断される根拠がないままに、従業員のスキルや経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事自体を与えなかったりする行為です。 たとえば、長年勤めたスキルのある従業員に対して簡単な雑用を押し付けるようなケースが挙げられます。 こうした行為は、被害者の自己肯定感低下につながるほか、ストレスによって退職に追い込む可能性も否めません。
過大な要求を出す
過大な要求とは、遂行不可能な業務を強制する行為を指します。 たとえば、長期間かかる業務を一日で済ませるように指示をするケースが挙げられます。また、罵倒や暴力といったほかのパワハラと組み合わせて、より陰湿なパワハラにつながる事例も少なくありません。 こうした、明らかに困難で不可能な要求は、被害者の心身に大きな負担をかけ、過労死や自殺といった深刻な事態を招く可能性も考えられるでしょう。
ハラスメントが起きる原因
ハラスメントが起こる背景には、認識不足や立場の悪用といった原因が潜んでいます。ここでは、パワハラに限らず、ハラスメント行為が起きる原因を4つ解説します。
ハラスメントへの認識不足
認識不足は、ハラスメントが起こる大きな原因のひとつです。パワハラに関しては、適切な指導との違いを理解していないケースが多く見られ、気付かないうちに相手を精神的に追い詰める可能性があります。 従来の職場では、上司が部下に対して厳しく指導をすることが当然という風潮も見られました。その流れで、厳しく叱責を続けたり、業務上のミスに対して人格を否定するような発言をしたりすれば、意図せずパワハラに発展してしまうでしょう。
立場の悪用
職場において、上司や先輩などの立場にある者が、その優位性を悪用して部下や後輩に不当な行為をするケースもパワハラの典型的な原因です。 たとえば、権力を利用して理不尽な命令をしたり、個人的な利益を目的として部下を利用したりすることが挙げられます。 一般的に、部下と比べて上司には強い権限が与えられており、役職者であればある程度のわがままは許されると考える人も少なくありません。一方で、部下側も、上司の意見だからと諦める可能性があります。こうした誤解がパワハラにつながるため注意が必要です。
価値観や考え方の違いの理解不足
職場における価値観や考え方の違いの理解不足は、パワハラ発生の一因となります。世代間や個人間での価値観の相違を認識しないまま指導を行うと、意図せず相手に苦痛を与える可能性が高いでしょう。 たとえば、成果や数値への過度なこだわりを部下に強要するほか、飲み会への参加は仕事の一環と考え、断る部下に対して冷遇する行為が挙げられます。 「厳しい指導こそ成長につながる」という新人教育の方針から、厳しいノルマや仕事量を経験させる指導方法の価値観の押し付けもパワハラにつながる原因です。
コミュニケーションスキルの不足
職場におけるコミュニケーションスキルの不足も、パワハラを引き起こす原因のひとつです。管理職が感情的なコミュニケーションを取ると、部下の人格を否定するような言葉や威圧的な態度につながりやすくハラスメントに該当する可能性があります。 上司が部下の業務上の問題に対し、現状把握や改善点の指示をせず、ただ叱責するだけでは信頼関係は築けません。 上司が自身の指導方法を客観的に認識できていない場合、部下が不快な思いをしていることに気づかないことがあります。
パワハラにならない指導方法
パワハラを避けるには、正しい指導方法を理解することが大切です。ここでは、パワハラにならない指導方法を解説します。
叱る目的を考える
部下を叱る際には、なぜ叱る必要があるのかという目的を検討しなければなりません。叱る行為の本質は、部下の行動を改善して成長を促す点です。しかし、感情的になれば叱る目的が曖昧になり、パワハラと受け取られるリスクが高まります。 たとえば、部下のミスに対して目的なく怒鳴りつけるだけでは、改善策が示されず、萎縮してしまう可能性があるでしょう。その結果、部下の成長を妨げ、職場の雰囲気も悪化するおそれがあります。こうしたトラブルを避けるためにも、叱る際には冷静さを保ち、改善点を伝えることが大切です。
指導の理由を明確に伝える
部下を指導するうえで、理由を明確に伝えることが重要なポイントです。指導した内容は、部下が自身の行動や成果を理解し、改善に取りくむための指針となります。 単なる叱責や命令ではなく、業務改善のために必要な指導であることを伝えましょう。たとえば「作業手順の遵守が生産性向上につながる」といった問題点を指摘できれば、部下も指導を受け入れやすいでしょう。 このように、できるだけ具体的に理由を伝えることで、指導がパワハラと受け取られるリスクが軽減され、部下の成長を促せます。
改善方法を提示する
指導をする際は、具体的な改善方法を提示することが大切です。これにより、部下は自身の課題を明確に理解し、適切な対策を講じやすくなります。 具体的な改善策を示さず、抽象的な批判や否定を行うだけでは、どのように改善すればよいか伝わりません。その結果、パワハラと受け取られる可能性も考えられるでしょう。 具体的な改善策として「ミスを減らすためにダブルチェックをしよう」といった指示が挙げられます。明確でわかりやすい改善策を提示できれば、部下は自分の行動を見直して、成長する機会が得られます。
相手が理解できるように伝える
パワハラを避けて指導するためには、相手が理解しやすいように伝えることが重要です。曖昧な表現や専門用語が多いと、指導の意図が伝わらず、混乱やストレスを引き起こす原因になります。 指導する際は、簡潔で具体的な言葉を使い、相手の理解度に合わせて説明しましょう。伝え方が不適切な場合は、パワハラと誤解される可能性があるため、相手の立場やスキルを考慮して伝えましょう。
感情的にならない
指導の場面で感情的にならないことは、効果的なコミュニケーションを維持し、パワハラを避けるために重要です。感情的な反応は、指導の意図を歪め、相手に不安や抵抗感を与える可能性があります。 冷静さを保つためには、アンガーマネジメントが有効です。たとえば、怒りを感じた際に6秒間待つ、その場を一時的に離れるといった対策があります。 冷静で客観的な態度は、信頼関係の構築や、組織全体の健全なコミュニケーション環境を促進します。
指導を改善させる方法
パワハラを防ぐには、従来の指導方法を改善させることも重要です。ここでは、パワハラにならない適切な指導を学ぶ方法を4つ解説します。
ハラスメントについて正しい知識を知る
パワハラを防ぎ、適切な指導を行うには、ハラスメントに関する正しい知識が必要です。ハラスメントの定義や種類を理解することで、無意識のうちに相手を傷つけるリスクを減らせます。 ハラスメントには、パワハラ以外にも性的な言動で不快感を与える「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」や精神的な苦痛を与える「モラルハラスメント(モラハラ)」などがあります。 これらに該当する行為を正しく認識することは指導とパワハラの違いを理解するうえでも重要なポイントです。
コミュニケーション力を向上させる
パワハラ防止に向けた効果的な指導を行うには、コミュニケーション力の向上も欠かせません。 コミュニケーション力が乏しいと、意見の食い違いにつながり、信頼関係を築きにくくなります。その結果、いくら適切な指導を行っても内容が適切に伝わらない可能性があるでしょう。 指導を行う際は、相手の話に耳を傾ける傾聴力が求められます。加えて、相手の立場や感情を理解し共感する共感力も重要になるでしょう。 こうしたスキルを高めることで、相手は理解されていると感じ、指導を受け入れやすくなります。
個人の能力にあった業務を与える
業務に関するスキルや知識は、従業員によってさまざまです。パワハラを避けるには、個人の能力を踏まえて、適切な業務を与える必要があります。部下のスキルや経験を無視した仕事を割り当てると、過度なストレスを与えたり、逆に成長の機会を奪ったりする可能性があるため注意しましょう。 個人の適性や成長段階に応じた業務配分によって、適切な指導とパワハラの線引きが明確になり、よりよい職場環境の構築につながります。
感情をコントロールする
感情のコントロールも、指導方法を改善するうえで重要なポイントです。感情的になってしまうと、いくら指導内容が良くても相手への叱責や攻撃と受け取られてしまい、パワハラと誤解される可能性があります。 感情のコントロールができれば、パワハラを防止しながら、より効果的な指導をすることが可能です。
外部から指導方法を学ぶ
自社で指導方法を改善できない場合は、外部から学ぶ手段も効果的です。知識やスキルがないまま自己流で指導をすると、無意識のうちにパワハラと受け取られる言動をする可能性があります。専門家から指導方法を学ぶと、スムーズに指導スキルが身につくでしょう。
また、第三者の視点からフィードバックを受けることで、見逃していた課題を把握できます。
クリエイティブアルファでは、課題解決につながる体験型研修を実施しています。要望を踏まえた企画が可能であり、パワハラ防止に向けた研修を検討している方にもおすすめです。
クリエイティブアルファの店長研修では、短期間で店長に必要なマネジメントスキルを習得できます。店舗の具体的な課題に合わせた研修を企画いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
パワハラは、職場内の優位性を利用して相手に苦痛を与える行為であり、成長を促す「指導」とはまったく異なります。 パワハラを防ぐためには、コミュニケーションスキルの向上や感情のコントロールなどを身につけることが大切です。自社で対応しきれない場合は、外部の講師に依頼する方法もよいでしょう。 クリエイティブアルファでは、パワハラ防止に向けた研修をはじめ、状況に合わせて効果的な研修を企画しています。参加者が楽しみながら主体的に学ぶことができるため、研修内容がしっかりと定着し、実際の業務に活かすことができます。 店舗課題を根本から解決し、社員一人ひとりが成長できる環境づくりをお手伝いいたしますので、研修を検討中の方は、お気軽にご相談ください。